京都府公立高校入試 前期選抜 英語の傾向と対策 ~過去5年分を徹底分析~
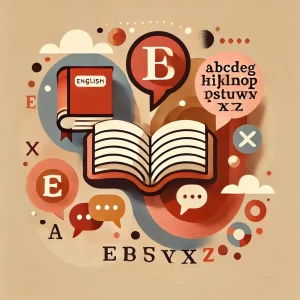
試験の全体像
京都府の公立高校入試前期選抜における英語試験は、一貫して3つの大問で構成されており、安定した出題形式が維持されています。総配点は40点前後で、筆記試験とリスニング試験に分かれています。ここでは、過去5年間(2020年度から2024年度)の筆記試験部分を中心に分析していきます。
特徴的な出題傾向
近年の試験問題を分析すると、実生活に即した実践的な英語力を測ることに重点が置かれていることが分かります。第1問では、日常的な会話場面が設定され、適切なコミュニケーション能力が問われます。特に、3-4語程度の英作文を通じて、自然な会話の流れを理解しているかどうかが評価されています。
第2問では、現代社会を反映した興味深い傾向が見られます。例えば2024年度の試験では、外国人観光客への対応に関するグラフを用いた出題がありました。また、2023年度ではアプリの利用方法を題材とした長文が出題されるなど、現代的なコンテキストが積極的に取り入れられています。
最も配点が大きい第3問では、物語文やスピーチ文などの長文読解を通じて、より深い理解力が求められます。単なる内容理解にとどまらず、登場人物の心情や文章の展開を考える力、そして自分の意見を英語で表現する力が問われています。
注目すべき変化と対策
過去5年間で特に注目すべき変化は、情報処理能力を問う問題の増加です。グラフや表の読み取り、複数の情報を関連付けて考える問題が定着してきています。このような問題に対応するためには、日頃から英字新聞やウェブサイトなどで、図表を含む英文に触れる機会を作ることが効果的です。
また、英作文の出題形式も少しずつ変化しています。以前は単純な和文英訳が中心でしたが、最近では場面に応じた適切な表現を選択する力や、自分の考えを論理的に組み立てる力が重視されています。このため、基本的な文法規則の理解に加えて、実践的な表現力を養うことが重要になってきています。
効果的な学習方法
受験対策としては、まず中学校の教科書内容の完全習得が基礎となります。特に、基本的な文法事項や頻出動詞の活用については、確実に理解し、運用できるレベルまで高める必要があります。
その上で、実践的な英語力を養うために、以下のような学習を行うことをお勧めします:
日常的な会話表現の習得
- 教科書の会話文を音読する
- 場面に応じた適切な表現を学ぶ
- 基本的な表現を自然に使えるまで練習する
長文読解力の向上
- 時間を計りながら読む練習をする
- 文章の構造を意識して読む
- 要約や感想を英語で書く練習をする
図表を含む問題への対応
- 様々な形式のグラフや表に慣れる
- データの比較や分析を英語で表現する
- 実生活に関連した統計資料を読む
これらの対策を計画的に進めることで、試験本番での実力発揮につながるでしょう。また、過去問演習を通じて、時間配分や解答の書き方などの技術的な面も確認しておくことが重要です。
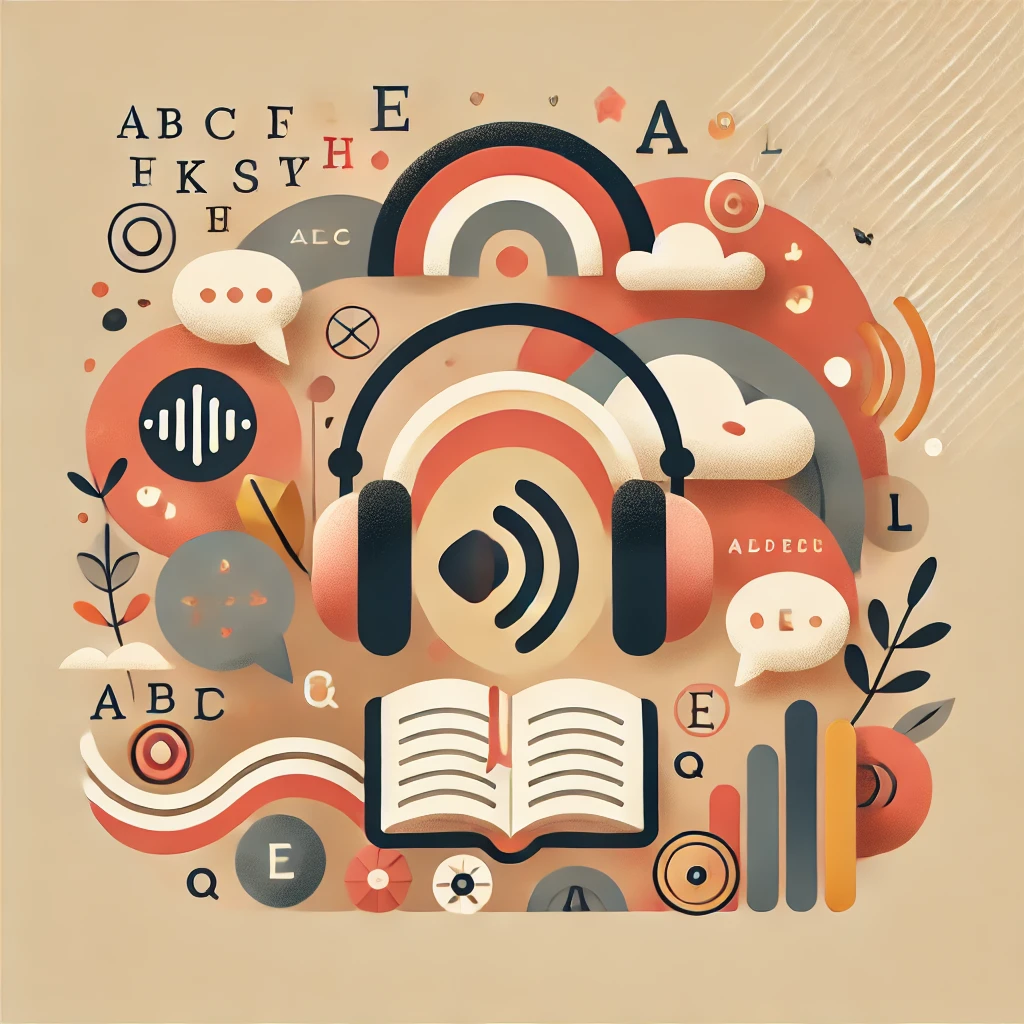
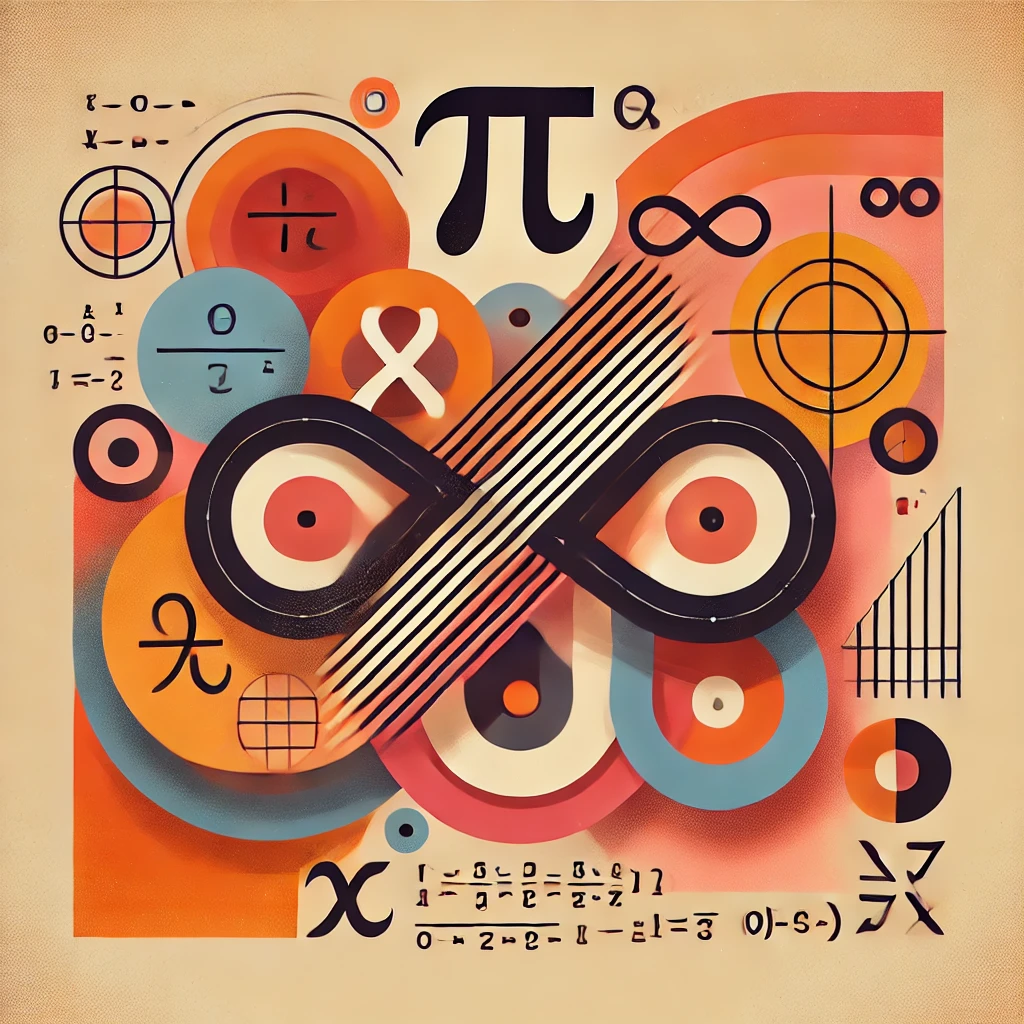
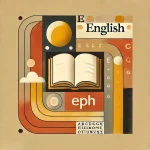

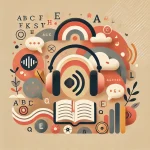
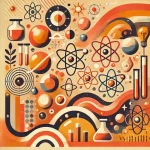
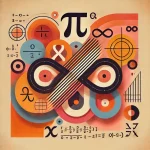
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません